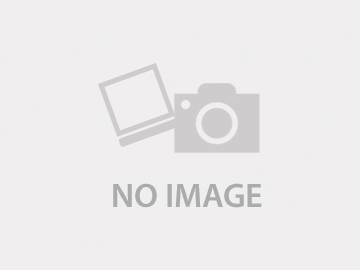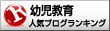ざっくりと保育園に関係しそうなところだけ読み込んでみました。その結果、色々と考えさせられる情報が出てきました。
個人的に気になったポイント
副食費(給食材料費)は施設での徴収が原則となるという結論が変わることはなかったようです。これは全私保連なども頑張ったそうなのですが、押し返すことが出来なかったそうです。
アレルギー児や宗教上の理由などで特別の給食を提供しているとしても、他の児童と同じ金額で徴収しなければならないことが明記されました。
また、給食材料費についても委託費と同様に途中入退園の日割り計算を行っても良いという書き方となっています。
10月以降は給食材料費の免除対象者を市町村の責任で選定し、誰が免除対象者なのかを施設側に通知しなければならなくなりました。その際にマイナンバー等を活用することが考えられますが、他の市町村から管外委託を受けている子どもたちについては、少し手続きが面倒になりそうな気配です。
免除対象者として通知された子どもについては、施設側は給食費の徴収が出来ません。そのかわりに加算が市町村から受けられます。加算の月額は4,500円となります。
ちなみに給食費として保護者から5,000円徴収していたとしても、加算として受け取れるのは5,000円に限られます。
滞納があった場合には、回収する責任は施設側にあります。
徴収に関して施設に補助金等は出ないので、面倒だけが降ってくる形です。
徴収事務を市町村が行うことが出来ないと明確に記載されてしまったので、他の方法はないかな?と思っていたら、「児童手当からの特別徴収」という方法が示されました。学校給食や保育料についても滞納している保護者については、この方法で市町村が児童手当から予め差っ引いてしまう方法があるようです。そして、差っ引いた金額を施設に支払うことが出来ます。
ピンときたのは、この方法を使える人は基本的にこの方法にしてもらえれば、施設はとりっぱぐれが無くなるのではないか?ということです。最も、児童手当は年3回しか支給しないなど、入金までの間、施設側のキャッシュフローが悪化するデメリットがあります。また、公務員の場合は市から児童手当が支給されるのではなく、公務員共済のような団体から支給されるらしく、その場合は差っ引くことが出来ないようです。
資料のリンクとそれぞれの中でのポイントとなりそうな部分については、下記の通りまとめました。
【児童福祉法第56条第7項、第8項】
第56条 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第7項 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第24条第1項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第2項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第1号 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第28条第2項第1号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
第2号 子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第2項第2号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第27条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
第8項 家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第24条第2項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第1号 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(第3号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第29条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第30条第2項第1号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
第2号 特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第30条第2項第2号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
第3号 特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第30条第2項第3号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
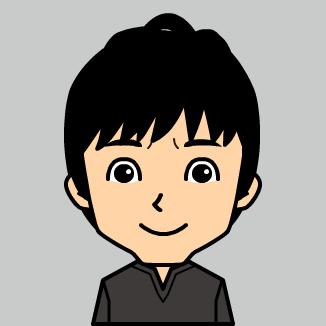
元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。