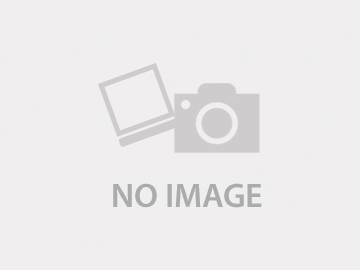2019年2月18日に内閣府の子ども・子育て支援新制度説明会が開かれて、資料が公開されていましたね。
2月18日子ども・子育て支援新制度説明会 【都道府県等説明会】
保育園に関係する部分をいくつか抜粋してご紹介したいと思います。
次第(抜粋)
第2部(12:30~17:00)
○行政説明
- 平成31年度当初予算案について
- 幼児教育の無償化について
2-1 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案について
2-2 幼児教育の無償化の実施に伴う主な事務について
2-3 幼児教育の無償化に関する予算等について
2-4 幼児教育の無償化に関する実務のフローについて
2-5 幼児教育の無償化に関するFAQについて
2-6 食材料費の取り扱いについて
2-7 平成31年度幼稚園就園奨励費補助について
2-8 幼児教育・預かり保育の無償化に係る留意点(幼稚園関係)
2-9 実費徴収に係る補足給付を行う事業の充実について
2-10 認可外保育施設の質の確保に向けた取組について
2-11 認可外保育施設に係る経過措置期間における無償化の対象範囲について
2-12 障害児の発達支援について- 平成31年度の公定価格(案)等について
3-1 平成31年度公定価格の対応について
3-2 平成31年度上半期単価表(案)
3-3 留意事項通知について
3-4 処遇改善等加算の基準年度の見直しについて
3-5 子どものための教育・保育給付交付金交付要綱(案)
3-6 公定価格に関するお知らせ事項- 処遇改善取得促進事業について
- 子ども・子育て支援全国総合システムの運用改善等について
- 地域子ども・子育て支援事業について
6-1 交付要綱(案)及び執行スケジュールについて
6-2 一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)の充実について
6-3 利用者支援事業、ファミリー・サポート・センター事業の充実について- 第二期子ども・子育て支援事業計画の作成等について
- 子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しについて
- 保育教諭の資格の特例と教員免許更新制度について
- 放課後児童クラブについて
10-1 新・放課後子ども総合プランについて
10-2 放課後児童クラブに関する地方分権に係る提案について- その他
11-1 連携施設について
11-2 10連休対応について
【資料2-5】幼児教育の無償化に関するFAQについて
38ページ以降に給食材料費に関するQ&Aが出ています。
- 施設が利用者から直接徴収すること
- 実際にかかった費用に応じて各施設が設定することが基本となること
- 利用調整を受ける2号認定子どもについて、材料費負担が著しく重たくならないように配慮する必要があること
- アレルギー対応などで費用が他の子よりもかかったとしても、その子にだけ多めの実費徴収はせず、実費徴収の金額は施設全体としてかかった食材料費を利用児童数で割って計算すること
- 欠席の場合や休園日がある場合、保護者の理解を得た上で保護者に対する請求額を減額することは可能
全体的に何もはっきりしたことは決まっていない印象ですが、「施設が利用者から徴収すること」を明記されたのは厄介だと感じています。
一方で、喫食数に応じて児童別に金額を使い分ける必要はないことも明記されました。アレルギー対応が必要な子どもだけ金額が増えるようなことはしなくて良い事になりそうです。
欠席した場合は減額するのが国の方針のようですが、欠席がわかるのは前日とか当日で、その時点では発注内容をキャンセルできないことを国はどこまで理解しているのでしょうか?欠席することも見込んで予め高めの請求単価にしてもよいということなのでしょうか?こんな程度の矛盾に気が付けないほど官僚(とそこで働いているコンサルタント)は仮設設定力が足りていないのでしょうか。
【資料3-1】平成31年度公定価格の対応について
2019年4月からは「処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)の1%上乗せ」、2019年10月からは「消費税10%への対応」「幼児教育の無償化への対応」「非常勤栄養士の配置(週3日程度)で栄養管理加算が取れること」「チーム保育推進加算の取得要件を平均勤続年数12年以上に緩和」などがあります。
消費税増税と幼児教育無償化の影響を受けて、2019年度は年度の途中で公定価格が変更される可能性があるということだと思います。保育事業者はどんどん事務作業が増えていくのに、その分の加算(事務職員雇上加算)はほとんど変わりません。保育制度に力を入れている政治家に直接働きかけないといけないかもしれませんね。
【資料3-2】平成31年度上半期単価表(案)
平成31年度(2019年度)の上半期の公定価格単価案が載っています。すでに次年度予算を策定されている園長先生もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、毎年この時期に価格改定と来年度価格の通知がされるのは大変めんどくさいです。まあ、予算とかと関係するので仕方がないとは思いますがどうにかならないもんですかね。
【資料3-4】処遇改善等加算の基準年度の見直しについて
2020年度以降の処遇改善等加算Ⅰ、加算Ⅱの”基準年度(平成24年度等)”を”前年度”にする方向で検討中とのことです。誰かの役に立つかな?とか思って平成24年度の俸給表と今年度の俸給表を入れるだけで、賃金の増額分、法定福利費の増加分などを自動計算するエクセルを作っていたのですが、これで私の労力は無駄になってしまいました。(後1年あるから頑張ることもやぶさかではないのですが。。。)
【資料8】子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しについて
① 幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格特例、② 幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得の特例について、特例適用期間を5年間延長する
そりゃ、保育者が足りなくて困っているこの状況で「資格を両方持っていないから認定子ども園では働けません」とやってしまうと、非難轟々ですよね。でも不思議なのは、「幼稚園教育要領と保育所保育指針の3歳以上児の教育部分と幼保連携型認定こども園教育・保育要領の内容を同じにした」と鼻高々に宣言している人たちが、それぞれの施設で働ける資格者を分けているのはなぜなのでしょうか?この辺、真正面から突っ込んでも多分官僚には勝ち目が無いので、あまりやりたくありませんが、本質的におかしいなと思いませんでしょうか。
【資料11-2】10連休対応について
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、10連休(保育所は通常土曜日開所のため9連休)となる件について、
-
- 休日等(日曜日や祝日)に常態的に休日保育を実施している保育園等は開所せよ
- 今回の10連休のみ保育が必要となる場合には、一時預かり事業や子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)により対応せよ
ざっくり解釈するとこんな感じでした。
後述する資料6-1-1でも触れられていますが、一時預かり事業を実施している事業者は10連休の間に預かる場合、児童1人あたり2,260円の加算を受けられるようです。これを高いと見るかやすいと見るか。通常の日曜日であれば、児童1人あたり800円ですから、破格なのかもしれませんね。でも、10連休の価値は通常の日曜日の3~4倍を超えるような気もしますがいかがでしょうか?
【資料6-1-1】子ども・子育て支援交付金交付要綱(案)
地域子育て支援拠点事業などいわゆる13事業に関する交付金が増額していますね。えっと、現行の金額よりも事業者として受け取る金額がだいぶ少ないような気がしていますが、これは後ほど自治体に確認してみようかな。。。
一時預かり事業のところで、10連休に受け入れをした場合の加算額が載っていますね。
これだけを見ると、一時預かり事業を実施していない保育所・幼稚園・認定こども園が10連休だけ開けた場合はどれだけの金額を出すつもりなんでしょうか。よくわからないですね。
頭の体操として次のような仮説を立ててみました。本当かどうかは分かりません。
- 常態的に一時預かり事業は行っていないが、2019年の10連休期間に限り、一時預かり事業を行う
- 1日あたりの園児数は60人(内訳:0歳児6人、1歳児9人、2歳児9人、3歳児13人、4歳児13人、5歳児14人)とする
- 必要な保育士は0歳児2名、1・2歳児2名、3・4・5歳児2名(国基準の最低限の職員数)の合計6名とする
- 通常の年に祝日だった4月29日、5月3日、5月4日、5月6日と振替休日の5月6日は受け入れしないが、2019年に限り祝日となる4月30日、5月1日、5月2日の3日間は上記60人を職員6名で11時間開所する(延べ利用児童数180名)
- 一時預かり事業の基本分をみると、年間延べ利用児童数が300名未満の場合は基準額が1,600,000円となる。一時預かり事業の年間開所日数は知らないが、仮に240日とすると、3日間開所の基本分は20,000円となる
- 利用児童数60名✕3日=180名につき、2,260円の加算を受けるとして、加算分は406,800円となる
- 保育士の平均年収3,410,500円から1時間当たりのコストは1,640円となる(年間2,080時間勤務と仮定)ので、6人✕8時間✕3日間✕1,640円✕休日出勤分1.5倍=354,240円
- 費用(人件費のみ)は354,240円で、収入は426,800円となるので差引収入72,560円となります
机の上の計算なのでそんな簡単ではないと一蹴されるかもしれませんが、こういう考え方もあるのではないかな?と思っています。どんな園長先生が7万円のために保育士の貴重な連休を捨てさせるのでしょうかね?福祉の心で開所させるのでしょうかね。ちなみにうちの園では開所しない方向です。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。