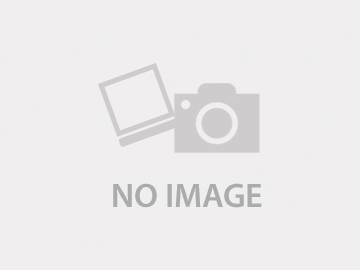自分への戒めというところが多いかもしれませんが、とにかく話す言葉書き言葉が難しくなりがちなのが、私個人として反省するところです。
今日は、園長先生特に違う畑から保育の世界に飛び込んだ園長先生に向けたお話です。
保育士さんは園長先生の言葉を理解していますか?
私が保育の世界に入ってきて数ヶ月が立った頃、当時の主任保育士から、
「多分正しいこと、素晴らしいことを言ってるんだと思いますが、保育士たちには届いていないと思いますよ」
と言われたことがあります。
定期的に思い出すように、Google Calendarでリマインダーを設定しているのですが、気がつくと「小難しい言葉」を使ってしまっています。これは前職でコンサルタントとして使っていた言葉が抜けていないだけの話なのですが、実は保育の世界でもとても大切なことを示しているのだと思います。

相手に伝わって初めて意味がある
保育士さんたちは日々、子どもや保護者、また同僚と接しています。子どもの発達によっては言葉では意思疎通が出来ないことがあるのは当然なので、それぞれの発達に応じて話し方やコミュニケーションを工夫していると思います。では、保護者や同僚に対して、同じように話し方やコミュニケーションを使い分けているでしょうか。
「同じ大人だから話せば分かる」「文章を読めばわかる」と疑いもなく日々のコミュニケーションを行っていないでしょうか。
これには大きな落とし穴があるかもしれません。そして、私は主任保育士からそれを教えてもらいました。
長年保育士として現場でバリバリ仕事をしてきて、先輩の背中を見て仕事を盗んで覚えてきた主任保育士からすると、最近の若い職員や若い保護者の中には、「日本語が通じない」と感じる人が増えてきたそうなのです。
これを聞いたときに、「日本語が通じない」のではなく、「当たり前」が主任保育士と若い人との間で違っているだけなのではないかな?と感じました。
コミュニケーションをするときに「言わなくてもわかることは言わない」「ここまで言えば意図は伝わる」という部分が実は多いのではないかと思っています。このような「当たり前」は同じような環境で育ってきて、同じような成長をしてきた人同士ではほとんど差がないと思うのです。(だから「当たり前」が同じなのです)
一方で、年齢や世代、育ち方や育ってきた環境が違う人との間では、「当たり前」が違うので、「言わなくてもわかることは言わない」だと「言わないことは伝わらない」となってしまうのです。だからどれだけ言葉を尽くしても「言わないことは伝わらない」ので、頑張ってコミュニケーションをとっても意味がないのではないかと思うのです。
ではどうすればよいのか?
相手によって言葉を使い分ける必要があるのだと思います。そして、基本的には相手が一番わかり易い言葉、例えば日本語の「ひらがな」のように、誰もが読めて、聞けて、理解できる言葉から始める必要があるのだと思います。
どんなに難しい漢字であってもルビが振ってあれば大抵の日本人であれば読むことが出来ます。読み方が分かれば辞書などを使って意味を調べたり、自分なりの意味付けを考えたり出来るので、少しずつ「当たり前」をすり合わせることが出来ると思うのです。
ですが、はじめから「難しい漢字」のような言葉で話してしまうと、相手は理解しようにも理解する手段がなくて諦めるしか無いのではないかと思っています。そうなると、相手を理解しようと思っていない人とコミュニケーションを取らなければならないため、非常に疲れてしまいます。疲れる相手とコミュニケーションを取るのはエネルギーが必要になるので、ますます疎遠になってしまいます。そうすると相手を理解したいとも思わなくなるので、「日本語が通じない」と諦めてしまうのではないか?と思っています。
そこまでする必要があるのか?
正直、全員に合わせて言葉を使い分けるのをいちいちやらないといけないとすると、非常にエネルギーが必要になります。出来ることなら避けたいです。相手がこっちの言うことを理解してくれれば良いのに、と思う気持ちも正直あります。
ですが、相手とコミュニケーションが取れないと、回り回って自分が苦しむことになるのではないでしょうか?
自分一人で何かをしているのであれば、他人に伝わるように頑張る必要はありません。ですが、保育の仕事に限らず何かしら他人とコミュニケーションが出来ないと、自分がやりたいこと、やらなければならないことは出来ないのではないでしょうか。
「他人のために自分が頑張る」と考えるとやりたくないかもしれませんが、自分のために自分が頑張るのであれば、多少やる気になるのではないでしょうか。
保護者にしっかりと子どもを見てもらいたいと思っている保育士が「お子さんの様子を見てあげてくださいね」と言った場合に、もしかしたら保護者は「私が子どもをぞんざいに扱っていると言いたいの?」と伝わってしまうかもしれません。そんなとき「今日保育園でお子さんがお箸を上手に使ってひじきをつまんでいたんですよ。ご家庭でも色々練習されているんですか?」と聞けば、保護者から家庭での様子を聞けるでしょう。保護者が子どもの様子をよく見ていれば、そこから話が膨らむでしょうし、よく見ていなければ「今日はお箸の使い方を見てみよう」と行動が変わるかもしれません。そして、別の日にお箸の使い方について、保護者から話をしてくれるかもしれません。
私自身への反省として
言葉は相手に伝わって、相手の行動や心情に影響を与えて初めて意味があると思っています。
先程の保育士の例ではありませんが、どんな言葉を使っても相手の行動や心情に変化をもたらさなければ、それは伝わっていないのだと思います。
このブログで書いている記事も、読んだ人に何かしら影響を与えて行動や心情に変化をもたらしたいと思っています。
コミュニケーションの理論や技術を学ぶだけでなく、何のためにコミュニケーションを学ぶのか?についてもしっかりと頭を整理して、技術を磨いていきたいなと感じています。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。