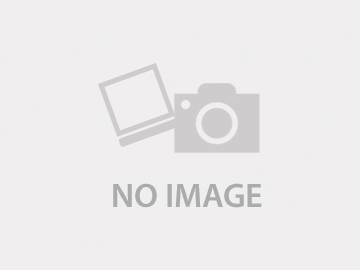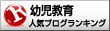保育者は子どもたちを育てることが仕事なのだが、保育者を育てるのは誰の仕事だろうか?
言うまでもなくそれは園長の仕事だ。
ということで、今回は園長の仕事として保育者を育てる方法について考えてみたい。
保育者を育てる方法
保育者を育てるということは、良い保育をする環境を整えるということです。
以前取り上げたOECDの保育の質の定義でもありましたが、保育の質を6種類に分けて考えています。
NHK解説委員室「保育の質とは何か」(視点・論点)
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/276807.html
「保育の質」とは、「子どもたちが心身ともに満たされより豊かに生きていくことを支え、保育の場が準備する環境や経験のすべてである」と言うことができます。つまり多面的で複合的なものです。国際経済協力機構OECDは図のように、志向性の質、構造の質など、6つの次元で捉えることができるとしています。
ここで言う「保育の場が準備する環境」というものの一つとして、「人的環境」があります。要は、保育士やその他の大人および子ども同士の人間関係やその人そのものが当てはまります。
ということは、保育者を育てることは、子どもたちが心身ともに満たされ豊かに生きていくことを支える環境を整備することと言えるのです。
あるべき姿を示す
ではどうすればよいのか?
一つの答えとして「園長があるべき姿を示す」ということがあると思います。
園長は保育園の様々な環境を整えることが仕事ですが、人を育てることが保育園の環境を整備することだと言えるので、これは園長の仕事となります。
そして、人を育てるときにどの方向に進めばよいのかを具体的に示すことが必要になります。
ですから、具体的に実践として「保育者としてどんな行動をするのが目指すべき姿なのか?」を示してあげる必要があるのです。
あるべき姿を実践する
あるべき姿を示した後は、保育者が実践してみる必要があります。
頭でわかっていても、体がついてこない、行動に落とし込めないと、自分であるべき姿に向かっていくことができないからです。
園長の仕事としては、「保育者があるべき姿を実践できる環境を整える」ということになります。
例えば、チャレンジしている保育者を応援したり、チャレンジできるようにその人が少し頑張らないと達成できない目標を設定したりすることがそれに当たります。
どうすればよいかを教える
実際にチャレンジしてみるとしても、やり方を教えてもらっていなければどうして良いのかわかりませんし、必ずと言っていいほど失敗します。
そんなことでチャレンジする勇気をくじいても仕方がないので、初めての人には特に「やり方を教える」ということが大切になります。
やり方を知らないのに、挑戦させて失敗させることは、今の時代では悪手だと思います。少なくとも言葉や文字でやり方を教えてあげなければできない人のほうが多いと考えたほうが良いと思います。
実践させる
やり方を教えた後は、実際に挑戦させてみましょう。
このときには「高い確率で失敗する」ということを想定しておく必要があります。そして園長の仕事としては、「失敗したときのカバー方法を考えて準備しておく」ということがあります。
失敗しても問題ないことのほうが多いと思いますが、失敗ばかりでは子どもたちが可愛そうですし、失敗の経験は挑戦した人にとってつらい経験となってしまいます。また、そのカバーが何もなければ、誰かが「急遽」カバーしなければいけなくなり、周囲の人に負担がかかります。それをあらかじめ避けるように準備しておくのが必要になります。
実践しているところを認める
チャレンジした人はうまくいくかどうかわからない状況で頑張っているのです。
だからこと、結果が伴っていようがいまいが、チャレンジした事自体を認めてあげる必要があります。
チャレンジすることが悪いことではなく、評価されることであると体験的に理解できた人は、次々とチャレンジしていくでしょうし、それほど高い確率ではないにしても何回に1回は成功することがあります。その「成功体験」は次もチャレンジしようという意欲に繋がります。
山本五十六は偉大だった
やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かじ
有名な言葉なので、聞いたことがある人も多いと思います。
まさに、人を行動させるためにはこの言葉の順番に実践していくことが必要なのだと思います。
そして、行動した人は失敗でも成功でも何かしらの「経験」を手に入れます。
経験を基礎に以前とは違う自分に変身することが、「成長する」ということではないでしょうか?
保育の現場で使えるかな?
そうは言っても保育の現場は毎日やらなければいけないことでてんやわんやとなっています。
上記のことは「やりたくてもできない」というのが現実ではないでしょうか?
ですが、「できないから」と諦めてしまったら人の成長は止まってしまいます。成長が止まった人たちに子どもたちが保育されているとすれば、その環境は果たして「子どもたちが心身ともに満たされより豊かに生きていくことを支え」る環境と言えるのでしょうか?
初めてだらけの保育の仕事でどこまで出来るか?
トライすることが大切
園長にとっても保育者を育てることは失敗する可能性の高い行動です。
だからこそ、園長が自ら「トライする」ことが大切なのではないかと思います。
トライアンドエラーは「エラー」が起きる前提
そのままですが、「エラー」を恐れて行動しなければ、トライもありません。トライがなければ失敗もありませんが、成功もまたありません。
経験という他に替えることができない貴重な資源を手に入れることはできません。
だったら「エラー」となることを前提にトライしてみるほうが良いと思いますが、いかがでしょうか?
「エラー」の後で何をするか?でその人の成長が変わる
失敗すること自体はそれほど悪いことではありません。
失敗して、その原因分析をしないことや失敗の結果次の挑戦をしないことが悪いことなのだと思います。
だからこそ、失敗したということは、次に成功するために何をすればよいか(何をしたらいけないか)をしる貴重な実験だったと考えて、次に繋げることがとても大切です。
失敗(エラー)のあとの行動こそが、成長スピードを決めます。何をするか?でその人が成長するかしないかが決まると言っても過言ではありません。
だからこそ、大いに失敗し大いに成長してもらいたいと思います。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。