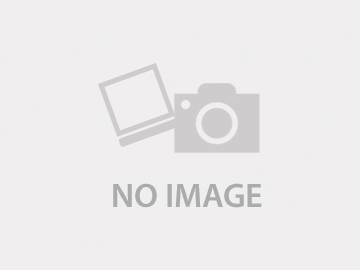先日小学校との連携についての会議があったので、そこで感じたことをメモしておく。同じような経験がある人は共感してもらえたらいいなぁと。
目的がよくわからない
とりあえず小学校区ごとに集まって話をする機会があった。
私の保育園に在籍する子どもは6校~8校ぐらいの小学校に進学するので、はっきり言って「小学校区」ごとに集まった所でごく一部の小学校としか連携ができない。あまり意味のない会議だなぁと感じながらとりあえず参加している。
多分、教育委員会が主催の会議なのでそういった感覚はあまり持ち合わせていないんだろうなと感じる。
それでもその小学校に進学する子どもがいないわけではないので、とりあえず参加しておく。
今回の会議では小学校の1年生の1学期ごろのアプローチカリキュラムと年長児の年度後半のカリキュラムを接続させようという試みなのだが、すでに3つの就学前施設から出てきている年度後半のカリキュラムがバラバラで整合性がなかった。そして、その3つのカリキュラムを整合させることは求めていないらしい。
何のために集まっているのか分からないが、小学校の先生としてはその3つのカリキュラムの違いをなんとかすり合わせて小学1年生のカリキュラムを作らないといけないらしい。それはそもそも無理なんじゃないかと思う。
「ためにする」作業が多すぎる
このカリキュラムを作って、教育委員会に提出する「事が必要」らしい。
教育委員会としては国が大方針を出しているので、それに従わざるを得ないのかもしれないが、そもそもの成り立ちが異なりすぎている施設間で整合しないことを「整合させるためにする」作業なので無駄な作業としか感じなかった。
バックグラウンドが異なる子どもたちが一つの施設で「統一した授業」を受けていくしか無い現状で、小学校教員が困っているから「統一した授業が受けられるためにする」カリキュラム作成に感じた。
違いを前提に、一人ひとりに寄り添った教育ができればそれで問題ないのではないか?と感じたが、そんな人的資本も時間的余裕も無いのだろう。無駄なことのために無駄な労力を割く意味のない会議だなと感じている。
それでも子どもの育ちにつなげるために
そんな大人の事情は子どもたちの将来の生活には関係しないので、とりあえず考えられる対処法を提示する。
- 小学1年生の指導要領にある項目を減らす
- 減らした指導要領に沿った授業を受けても進級できない子どもについては進級させないことを当たり前と考える文化を作る
- 小学校教員を倍増させて、指導に当たる時間とエネルギーを生み出す
- 学校がすべきことと家庭がすべきことを切り分けて、不必要な業務を減らす
色々と考えてみたものの、どれもこれも現実味がない。
ということは結局今のまま「地獄への一本道」を進むしか無いのだろうか。悲しい結末しか見えないが、今できることはその程度なのかもしれない。
理想を語る
理想としては、様々な就学前施設から進学してきた子どもたちは、一度どのような特質や得意不得意があるかを小学校の基準で図り直すのが良いと思う。
その上で、「教育」的側面から必要な支援を行い、基準に到達しない子どもについては3ヶ月とか半年とか遅れて進級する制度とする。
進級しない子どもが当たり前のように出てきたら、家庭でも「標準的な進級速度」に乗せるのか、標準よりも速い速度にするのか遅い速度にするのかを選ぶことが出来るようになるのではないかと思う。
そのためには、教科担任制とか学年の概念とかが一度壊されないといけない。保護者が進級の速度を決めて子どもにも選択権を与えて進級させる。
そうなると小学校は今でいう楽ちんな大学と似たようなものになるかと思う。
義務教育として小学校+中学校のカリキュラムは卒業させる義務を保護者は負うので、そのカリキュラムを終えさせることが保護者に求められる。その後の進路は飛び級で6歳が高校教育を受けていたり、20歳で高校入学したりする。
義務教育までは授業料を無償化してしまう。
そんな世界になれば、大学を出ても英単語が理解できないような人間は少なくなるだろうし、高校を出ていなくても立派に仕事ができる人がわんさか出てくるだろう。変な東京一極集中になることも減るだろう。
超高学歴のスーパーエリートはたくさん現れるだろうが、今の受験戦争を勝ち抜いて東大合格して官僚になるというようなモデルは少なくなると思う。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。