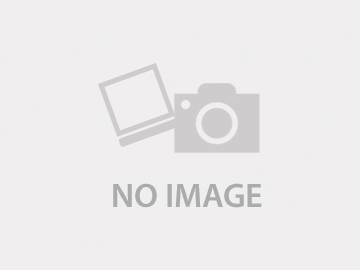保育の質を高めよう!という言葉は、この業界にいると耳にタコが出来るほど聞いていると思います。私も何度も使っています。
保育の質を高めるためにはどうすればよいのでしょうか?保育士が頑張ればいいのでしょうか?経営者が取り組むことはないのでしょうか?
そもそも保育の質とは何なのでしょうか?
この点についてNHKの解説委員室でまとめられていますので、一部引用します。
東京大学 秋田喜代美先生がまとめられているので、引用元を見ていただくのが一番良いのですが、少し抜粋してご紹介します。
保育の質を整理すると6つの切り口で整理できる(OECDの整理)
「志向性の質」
… 保育において何を大事にどのような保育の方向性をめざすのかという方向性や目標
「構造の質」
…施設の広さや備えるべき条件、また保育者一人あたりが担当する子どもの人数
「教育の概念と実践として内容や考え方」
…保育所保育指針や幼稚園教育要領等で定める他、各園が「子どもたちに乳幼児期に保障したい経験、活動」をどう考えているか?
「 保育プロセスの質」
…保育士と子ども達あるいは子ども同志のやりとりやその活動のための具体的な素材や遊具などの環境構成
「園としての実施運営の質」
…園として保育プロセスの質の向上に取り組んだり、効果的なチーム形成が出来ているか、チームで生み出す園の風土
「成果の質」
…保育によって本当に子どもにとって健やかな心身の成長が保障されているか
それぞれの次元・側面について、どれから向上させるのか?については、自園の保育の質が高いのか、低いのかによって変わるとされています。これは当たり前で、配置基準を下回っているような質の低い保育園が「保育プロセスの質」を高めるための活動を優先的に行うのは間違っています。
リンク先でも保育の質が低いところは「構造の質」を向上させることを優先すべきとしています。質が普通のところは「保育者の専門性の向上のための研修等」を進めるべきで、質が高い所はさらなる高みを目指すために、「保育者の経験年数、職場環境等を改善せよ」としています。
この切り口は「確かにそうだな」と思うところがたくさんありますが、いざ自園を振り返ってみて「さて、何から始めよう?」と考えると少し使い勝手が悪く感じます。個人的見解かもしれませんが。
多くの園長先生は「自園の課題はなんとなく整理ができているが、何が原因で何から手を付ければよいのか分からない」と感じているのではないでしょうか。そんな園長先生に「保育の質を向上させるためには、OECDの定義した6種類の次元で自園の状況を振り返って見ればよいのだよ!」と言っても受け入れてもらえません。
そこで、私なりの振り返りポイントを整理したいと思います。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」をクリアしているか?クリアしていないのであれば、何ヶ月以内にクリアすることが出来るか?(構造の質に関連)
認可保育所であれば「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」をクリアしていない施設はほとんどないと思いますが、認可外施設であればこの基準をクリアすることを目標にするのが良いと思います。国が示す「子どもの良好な生活のために”最低限クリアしておいてほしい”という考え・数値目標なので、状況によっては難しいとは思いますが、クリアしてもらいたいと思います。
マネジメントの観点からはヒトのマネジメントやモノのマネジメント、間接的にカネのマネジメントが関係してきます。
保育者一人あたりの子ども数が「園の定める」基準をクリアしているか?または「自分の園として最低限このレベルは維持しなければならない配置基準」をクリアしているか?(構造の質に関連)
たとえば国や市町村が定める配置基準として、1歳児6人に対して保育士1名だったとしても、自園が目指す保育を行うためには、1歳児4人に対して保育士1名が必要なのだとすれば、その基準をクリアしているかを考えていただきたいです。
もちろん、認可保育所であれば公定価格によって収入が決まってきてしまうので、基準以上の配置をすることは困難かもしれませんが、それをなんとかしなければならないと行動することは大切だと思います。
マネジメントの観点からはヒトのマネジメントやカネのマネジメントが関係してきます。
自園の保育目標は、本当に今目指している保育の姿と一致しているか?(志向性の質に関連)
保育目標は長らく変わってきていないという保育園が多いと思います。認定こども園の場合は「教育・保育目標」になるのでしょうか。ここで「保育目標」と呼んでいるのは、「自園がどんな保育を目指しているか?」「自園で育つ子どもたちにどんなふうに育ってほしいか」を示したものです。
多くの保育園では、過去にエネルギッシュな園長先生か理事長先生が決めた保育目標を今でも使い続けているのだと思います。そして、多くの保育園でその保育目標は有効に生き続けているのだと思います。
一方で、園長が代替わりし、保育園を取り巻く環境が変わってきたことにより、目指す姿を見直す時期になっている保育園もあると思います。自園が置かれた状況や目指す姿に合わせて、必要であれば保育目標を見直していけば良いと思っています。
マネジメントの観点からは保育目標の見直し、経営者の意識改革が関係してきます。
次のページでも見直しのポイントを示します。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。