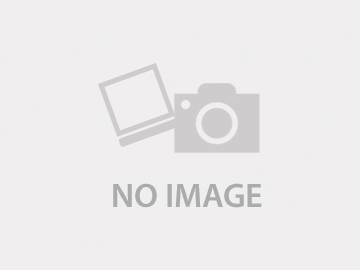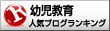子どもたちの体の中に流れる時間は大人とは少し違います。
今日は待つことについて書きたいと思います。
大人の時間・子どもの時間
子どもたちは自分が熱中しているときには時間の流れを忘れて取り組みます。逆に自分がやりたくないことをしている時には、大人以上に時間を長く感じています。
大人も体の中に流れる時間の長さが異なるのですが、その差は子どものほうが大きいものになります。
先日、給食の食パンの耳を残していた男の子がいました。耳が嫌いなため残したいけど一緒に食べているお姉さんとお兄さんがそれを許してくれませんでした。男の子にとってはなんとかやり過ごそうとしていたようですが、そこに私が来て「助けて」という目をしていたので、少し話をしてみました。
男の子は「もう食べた」と自分のお弁当箱にパンの耳を隠して嘘を付きました。周りのお兄さん、お姉さんたちが「違うよ、うそよ、食べてないよ」と口々に言うものなので、私が「○○君、耳食べてないの?」と聞くと、「ううん、食べたよ」と下を向きながら必死に嘘をついていました。
これは、自分の中で「ちゃんと食べなければいけない」という思いと、「嫌いだから食べたくない」という思いが交錯しているのがビシビシと伝わってきたので、私からは「迷う時間」をあげることにしました。
「じゃあ、もしまだ食べていなかったんなら頑張って食べてみてね。もう食べてしまっていたんならもういいよ」
それだけ言って、その場を去りました。
自分の気持ちを整理する時間
その子にとっては「食べていないことは見抜かれている」「自分で食べるまで待ってくれている」そう感じてほしいという願いからその行動を取りました。
しばらくしたら、自分でお弁当箱を開けて、中に残されていたパンの耳をしっかりと食べてくれていました。やはり自分の中で迷う時間が必要だったのだな、周りのお兄さん、お姉さんから色々言われて自分で決めることができなくなっていたんだなと感じました。
食べ終わりそうなときに先程の男の子のところへ行き、「おー!ちゃんと食べられたね」と声をかけてあげると、その子も「食べたよ!」と自信満々な表情で応えてくれました。
実に単純な話かもしれないのですが、こういった数分待つということが、保育の世界ではとても大切になります。
子どもにとっては、待ってもらえたこの数分、自分で決めるまで迷うこの数分がとても大切な時間で非常に長い時間だったのではないかと思いました。
大人は近い将来や遠い将来の見通しを持って行動するので、単純な行動一つ一つにある程度の時間を予め決めてしまっています。ですが、見通しを持つことが難しい年齢の子どもにとっては今がすべてであり、とても濃い時間を過ごしているのです。
子どもの体感する時間の長さに大人が身を置いて、その中でどういう言葉がけをすることが子どもに一番受け入れやすいのかをしっかりと考えることが、質の高い保育とも言えるように感じました。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。