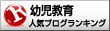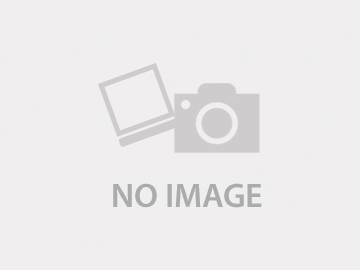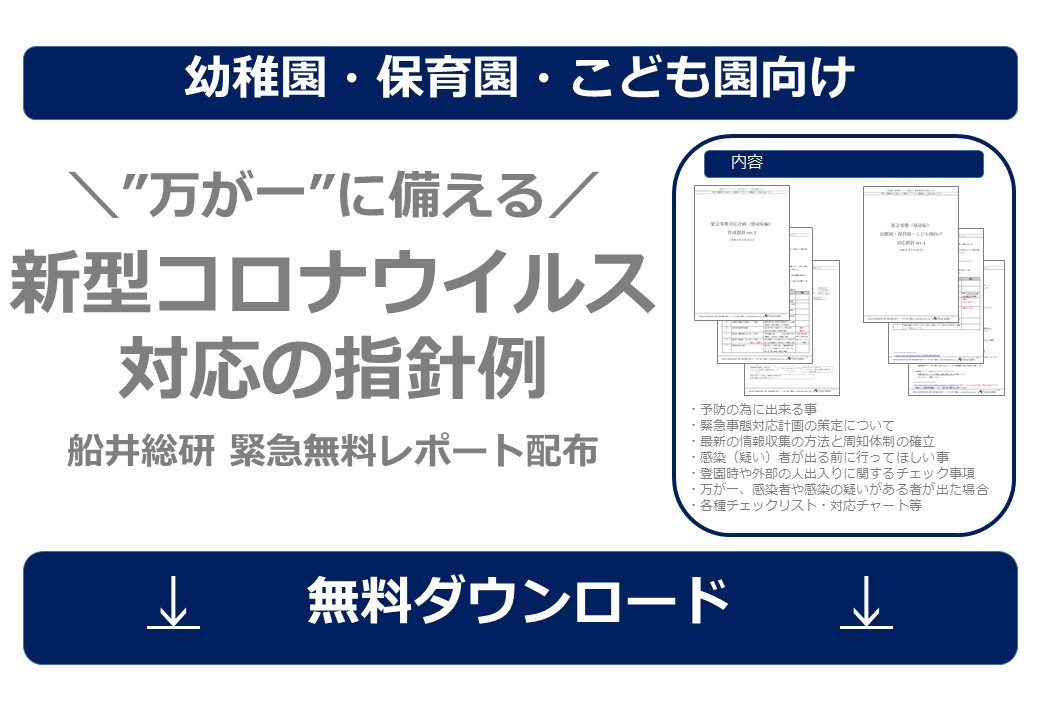子どもたちに対して「話を聞きなさい!」と怒っている保育士がいたので、少し様子を見て後から話を聞いてみた。
こうしなければならないの罠
どうも、その保育士は子どもたちが集まって一緒に絵本を読む時間だったにもかかわらず、一人で遊んで集団行動が出来なかったことに腹を立てていたらしい。その程度で腹を立てるというのはどうか?と思ったが、その保育士自身がなにかに腹を立てていたから怒ってしまったのではないかと思っている。
保育士に限らず、長年同じような流れで生活や仕事をしてきた人たちにとって「こうしなければならない」という罠が強力な効き目を現すことがある。これまでこうやって来たから、これからもこうしなければならないと思い込んでしまう罠だ。
果たして本当にそうだろうか?と、立ち止まって考えてみた時に「いや違うかも」と思えるのはまだましな方。そもそも立ち止まって考えることすらできなくなっている人は罠にどっぷり浸かっていて、さらに他人も罠にかけようとしている危険な人。
今までとこれからは同じではない
当たり前だが今までの経験がこれからも通用するとは限らない。状況も違えば実施者も受け手となる子どもたちもみんな違っている。
だからこそ、その時その時にしっかりと考えることが大切になる。また、考えることが出来るような時間的ゆとりと心理的ゆとりがなければいけない。
ただ、大前提として「今までとこれからは同じではない」という共通認識を持っていないといけない。
話を聞きたくなる仕掛けをどれだけ作れるか?
はじめの話題に戻すと、子どもたちが話を聞きたいと思わせるための仕掛けをどれだけ作れていたか?によって、子どもたちが話を聞くかどうかが変わってくる。
もちろん、「先生の話を聞かなければいけない」としっかりと”教え込んで”話を聞かせることは出来るかもしれない。でもそれは思いっきり管理的な保育をしていることになるだろう。
そんなことよりも、「この先生の話は面白そうだから聞きたい」と思わせることや、その前に「この先生が好きだからこの先生の話を聞いてみたい、聞いたら面白いに違いない」という関係性を作っておくことのほうが何倍も重要だと思う。
仕掛けを作ると書いたが、実際は「関係性を作る」という方が正しいだろう。
話を聞きなさい!と強制するのではなく、話を聞くのが当たり前で話を聞かないほうがムズムズするという関係性をどうやって作るか?を考えておかなければならないと思う。
Sponsored Links
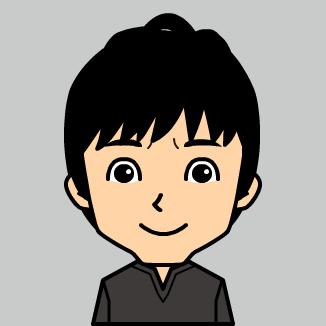
元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。