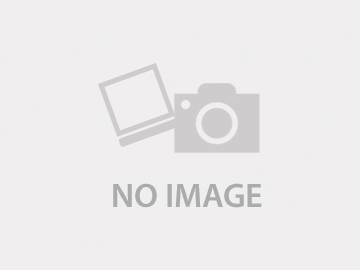先日小学校を当園の園児と一緒に訪問してきたのですが、今年もまたひしひしと恐怖というか不思議さを感じました。
全員が挨拶すること
これ自体は素晴らしいことなのかもしれませんが、違和感を感じました。
子どもたちを連れて小学校から帰るときに、すれ違う高齢者の方々は子どもたちの方を見て笑顔で「こんにちは」と挨拶してくれるのです。それに対して子どもたちも「こんにちは」と返しますし、その逆もありました。
一方、小学生はこちらの姿が見えたら反射的に「こんにちは」と言っているように感じました。何やら機械的な対応というか、挨拶の先にコミュニケーションを取りたいという気持ちが感じられずに「挨拶をすること」が目的であるように感じました。
一番の違いは高齢者の方々は挨拶のあとに「どこから来たの?」とか「どこへ行くの?」とか「どこの保育園?」というように、人と人の関わりを求めてきたということです。コミュニケーションのきっかけとして挨拶されたのだなぁと感じましたし、それが普通の姿なのではないかとも思います。
笛の合図で動くこと
一人の先生が20人から30人の子どもたちを効率的に動かすためには、笛の合図はとても効果的だと思います。ですが、一人ひとりに寄り添った関わりをする保育園での生活に慣れてしまうと、笛の合図で子どもたちが立ったり座ったりする姿を見て、恐怖を感じました。
まるでイルカショーやアシカショーの調教師を見ているようでした。小学校の教諭にはそんな意図は無いのでしょうが。
保育園に連れて帰ってください
小学校の先生がふざけたり上手くできなかった小学生について、みんなの前で「○○君も一緒に保育園へ連れて帰ってください。」と私達に言ったのです。流石に頭がクラクラしましたが、何も言えませんでした。
これは小学生に恥ずかしい思いをさせることで「適切な」行動をするように矯正、強制する振る舞いなのだと思いますが、やってることはなかなか残酷で失礼な行為です。
大人相手にこれをやったらブチギレる人がいると思うのですが、なぜ子ども相手に堂々とできる人が教員をやってるのでしょうかね?
軍隊みたいだな
小学校で様々な体験をして感じるのは、いつまで経っても小学校は軍隊みたいなところだなということでした。
教師という名の指揮官の言うとおりに子どもを育てることが目的となっているように思います。教師の考えとそぐわない子は非常に生きづらいですし、集団凝集性が強く働くでしょうから、いじめの問題なども無くならないでしょう。
同質な人を大量に育てることが求められる時代ならまだしも、現在ですら人と異なる考えを自身を持って主張したり、他者の異なる考えを尊重できる人が求められているにもかかわらず、小学校でこんなことしていて良いのかな?と悲しい気持ちになりました。
小学生時代にボロボロにされるかもしれないのですが、それまでの時間は自分のことが尊重される経験をたくさんさせてあげたいなと感じた小学校訪問でした。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。