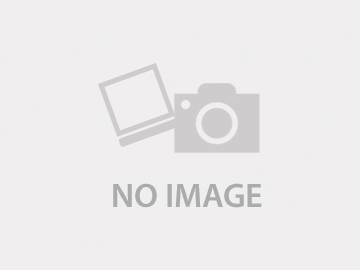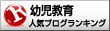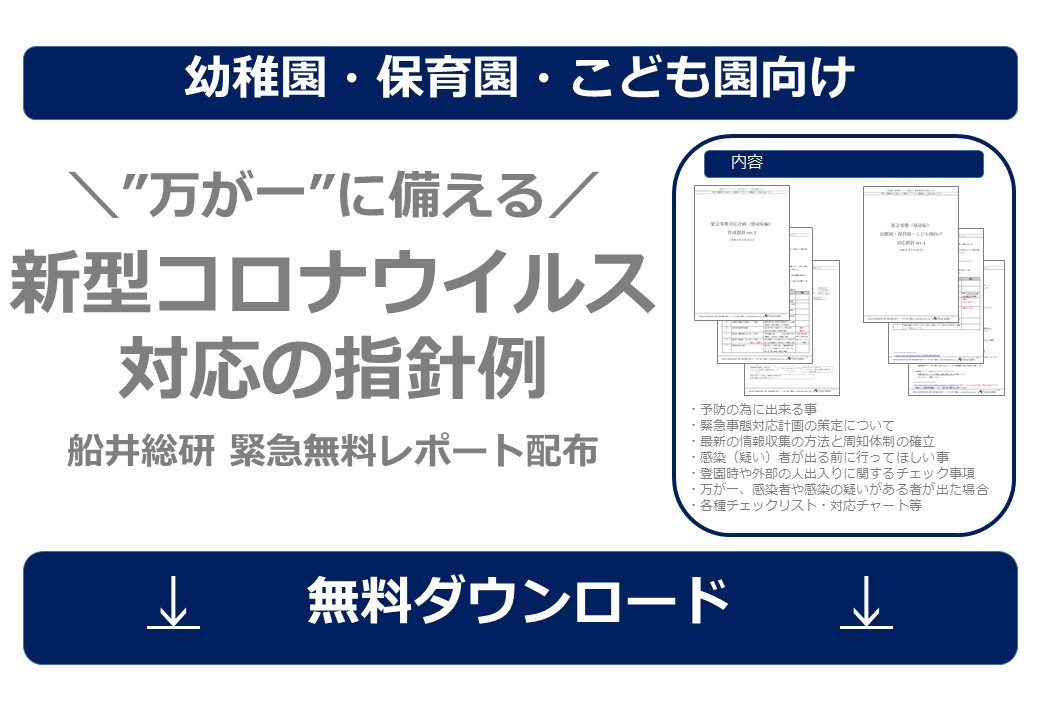保育士さんの中には「きちんとしなさい」や「きちんとして」というような言葉を多用している人も多いのではないかと思います。この言葉にはとても危険な側面があると感じているので、このことについて書いてみたいと思います。
「きちんと」って何?
辞書をひくとこの様になっている。
- よく整っていて、乱れたところのないさま。「洋服をきちんと着る」「部屋がきちんとしている」
- 正確な、また規則正しいさま。「集会時間にきちんと集まる」「家賃をきちんと払う」
- すきまや過不足のないさま。ぴったり。「帳尻がきちんと合う」
Goo辞書より引用
つまりは整っているとか正確であるとか過不足がないという意味のようだ。さて、この言葉は現代の日本では「正しい」というニュアンスが含まれていると感じる人は多いと思う。逆に「きちんとしていない」「きちんとしない」ことは「悪」であるという印象を受けるのも違和感ないだろう。
あるべき姿が想像できる
もう少し深堀りすると、この「きちんとしている」という状態は、「あるべき姿を想像して、その状態にあること」を指している事が多い。例えば「脱いだ靴をきちんとする」といえば、玄関で脱いだ靴を揃えておくことをイメージできる人が大半だろう。
そのことから「きちんとしなさい」や「きちんとして」という発言をする人の中には「○○の状況では△△の状態が”正しい”状態である」というイメージを持っているはずだ。一部あるべき姿をイメージせずに「きちんと」という人もいないわけではないが、少数派だろう。
あるべき姿になっていないのは、「相手側に責任がある」
そして、厄介なことに「きちんとしなさい」などを言う場合には「きちんとしていない」ことの責任は相手側にあると考えられているということだ。
「私が考えるあるべき姿になっていないのは、あなたに責任があるのだから、あなたがあるべき姿に変えなければならない」というのが「きちんとしなさい」の持つ言葉の影響力だ。
責任を果たせ
そして、「相手側に責任がある」となれば人は結構ひどいことを平気でしてしまう。自分がされたら顔をしかめるようなことも存外簡単にできてしまう生き物なのだ。それほど「きちんとしなさい」は恐ろしい側面を持っている。
責任を果たさない相手が悪い、責任を果たさないのであればそれなりの不利益を被っても仕方がない、私がやっていることは通常なら許されないかもしれないし、無関係の人にはできないことだが責任を果たさない相手に対してなら問題ないというように、どんどんと認知的不協和の解消が進んでしまう。
世の中に「きちんとしている」はどれくらいあるか?
上記のようなことを考えていくと、「きちんとしなさい」を使うことが怖くなってくる。だとしても、多くの人が「きちんとしている」ことを良しとするのであれば、世の中には多くの「きちんとしている」が溢れていることになるはずだろうと考えた。
例えば車を運転する人であれば制限速度や交通ルールをしっかりと守って走行している人が多数派で、「流れに乗っているから」などという理由で制限速度を超過する人は少数派のはずだ(そんなことは少ないだろう)
また、スーツを着ることが職務上求められる人たちは季節に関わらずネクタイを締めているだろうし、男性も女性も関係なくスーツを着ているはずだろう(スーツ発祥の国イギリスでもそんなことはなく、暑ければ短パンで勤務する人もいる)
あるべき姿は人それぞれで時代によっても変わる
色々と頭の体操をしていくと、ふと当たり前のことを思い出した。
あるべき姿は人それぞれ違っているのだ。そして、それぞれの「あるべき姿」は時代や環境によって容易に変わってしまうのだ。
そうなるとあるべき姿と同じ状態を「きちんとしている」と言われてしまうと、殆どの場合「きちんとしていない」=「正しくない」という結論になってしまわないだろうか。
無理を通せば心が壊れる
そんな事を考えずに「これがきちんとしている状態だから」と誰かのいうあるべき姿に合わせようとすると、必ずどこかの誰かが心を壊してしまう。なぜなら心を壊してしまう人にとっては「当たり前ではなく、あるべきではない姿にさせられている」のだから。
「きちんとしなさい」はその発言をする人にとってはとてもたやすく気持ちの良いことである一方、その発言を聞く人にとってはとても苦痛を伴うことになる可能性をはらんでいるのだ。
ただし、発言をする人、聞く人の双方にとって同じ「あるべき姿」がイメージできているのであれば、その発言に問題はなにもない。その点には注意が必要だ。
より自然に近い形で生きられる世界に
きちんとしていないことが当たり前で自然
人間の住む世界を考えてみたときに、「きちんとしていない」というのはごく当たり前の話である。それは人間が生物としてのヒトであることを考えれば、同じような生物が殆どの場合きちんとしていないことから考えて当然になる。
それでも集団で生きていくことが生物としての本能であるヒトは、ある程度共通の「あるべき姿」を共有しながら生きている。ただし、それは時代や環境や生きる場所生まれる場所などによっていとも簡単に変わってしまうものでもある。
「きちんとしていない」人が変化を作る
もし集団と自分の「きちんと」が同じであれば、違和感なくそれに従うだろう。仮に集団と自分の「きちんと」が異なっている時には、「こっちのほうがいいんじゃない?」と「きちんと」している状態を変えていくことが必要なのだろう。この手続を取らないで、「きちんと」していない人が行動を変えなければならないとしてしまうと、より良い状態に変われない。もしかするともっといい状態になれるかもしれないのに、「今のまま」を大切にした結果、みんなが辛く苦しい状態になっているのかもしれない。
変化を恐れずに、新しい考えを受け入れて検討してみる姿勢がみんなに備わっていれば、「きちんとしなさい」は減るのではないだろうか。
自然は失敗の繰り返しからより良い状態を選んできた
進化論に反対する意見もあるが、進化の過程は失敗を繰り返し、挑戦と突然変異を繰り返した結果、現状に一番適合した種族が生き残ってきた歴史でもある。
そうだとすれば、人間の生活においても「今まで通り」というのは進化の流れに反するものではないだろうか。進化の過程と同じように、失敗を恐れず新しいことにチャレンジすることで今をよりよく生きるためのヒントを手に入れることができるのではないだろうか。
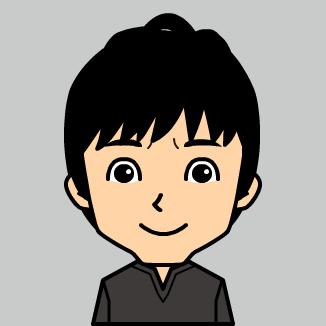
元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。