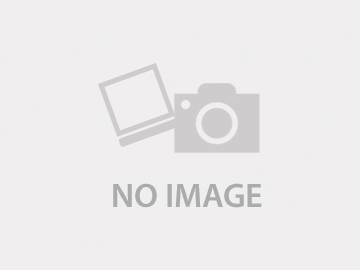保育園の経営者であればみなさんが思うことだと思いますが、「職員が早く成長して欲しい」と思うのではないでしょうか。
職員の成長は人によって違いがありますが、施設として組織としてどのように育てていけばよいのか、何度となく考えてこられたと思います。そして、思ったように成長してくれない職員に対して苛立ちやあきらめを感じられているのではないでしょうか。
職員の育て方について少し考えてみたいと思います。
育つスピードには差がある
職員の生育歴やこれまでの経験などから育つスピードには差が生じます。それはすぐに解消するものではないので、あるがままに受け入れるしかありません。その認識があるのか無いのかで育てる方のストレスが段違いとなります。
育てることはそもそもストレスフルな作業です。必要のないストレスは無くすようにしたほうが望ましいです。
育たない職員はいない
どんなに頑張っても報われないから、育てることは辞めてしまったという方もいるかも知れません。
育つスピードには差があると先ほど記述しましたが、成長速度は遅いかもしれませんが育たないわけではないのです。これも記憶しておいたほうが良い事です。
ただ、現実問題として育つスピードが遅い職員には高いレベルを求めることができなくなります。したがって処遇も高いものを与えることが出来ません。その結果、その職場でその職員が働き続けることはもしかしたら不幸になることなのかもしれません。その辺りもある程度経営者であれば織り込んでおかなければならないことなのかもしれません。
経営者が求めるものと職員が目指す物は違う
そもそも経営者と職員とでは見ている世界が違います。考えている物事の次元が違うので、求めるものは大きく異なってきます。
その場合に、経営者は職員が見ている世界まで降りていって(もしくは別の次元に飛び込んでいって)職員が目指しているものを理解しなければなりません。
ただ、職員が目指しているものを受け入れる必要があるわけではないのです。違いを認識し、その上で経営者は自分が目指しているもの、求めるものの「良さ」を伝えて職員が同じ方向を目指してくれるように勇気づけていかなければならないのです。
正直、この作業が一番エネルギーを使います。また、なかなか結果につながらない作業です。経営者の責任としてこの作業を行わなければならないから、経営者の処遇は高いのです。
目指す姿を一致させることが最重要
前述したように目指す姿を一致させることが最重要なのですが、では具体的にどうやればよいのでしょうか。
経営者のタイプや職員のタイプによって方法は様々なのですが、大前提として、経営者が目指すもの、目指す姿を誰もがありありとイメージできるところまで具体的に落とし込むことが必要になります。
その具体的なイメージを職員に伝えて「それって良いですね」と本心から職員が言えるようになったとしたら、目指す姿が一致していると言えます。もちろんその姿を実現するためにいくつもの課題をクリアしていかなければならないのですが、それはまた別問題です。
現状と目指す姿とのギャップを示して考えさせる
目指す姿を一致させることができれば、その目指す姿と現状との差(ギャップ)がどこにどれだけあるのかを明確にしていくことが必要になります。そしてそのギャップをどのように埋めるのか?が職員の育て方となります。
通常、経営者が全職員の現状とギャップを把握してそのギャップの埋め方を逐一確認することは非常に難しくなります。そこで、中間管理職的な職員の存在が重要になります。この職員をどのように育てるのか?が経営者の腕の見せ所となります。
出来ないことを責めない
色々と書いてきましたが、ここまでのプロセスを一発でうまく出来る人はほんの一握りしかいないと思います。そして、そのような人はこんな記事を読まなくてもすでに実践していると思います。
となると、私を含めた世間一般の人たちは、「出来ないこと」を責めても仕方がないのです。だって、ほとんどの人が出来ないような難しいことなのですから。
そして、成長しない人に対して「なぜ出来ないんだ」などと責めても意味がないのです。ただ成長できない人には以下のような特徴があるので、その中のどれに(単独または複数)該当するのかを明らかにして、解決策を考えさせて、必要に応じて経営者、中間管理職が関与して「どうすれば出来るのか?」を一緒に考えていくことが必要になります。

元コンサルティングファームでIT、ビジネス、内部統制、監査支援コンサルタントとして働き、今は保育園で園長業務を行う。
今をよりよく生きる大人がたくさんいる世界にしたいと思っています。そのために良い保育が出来る保育園を作りたいと思っています。